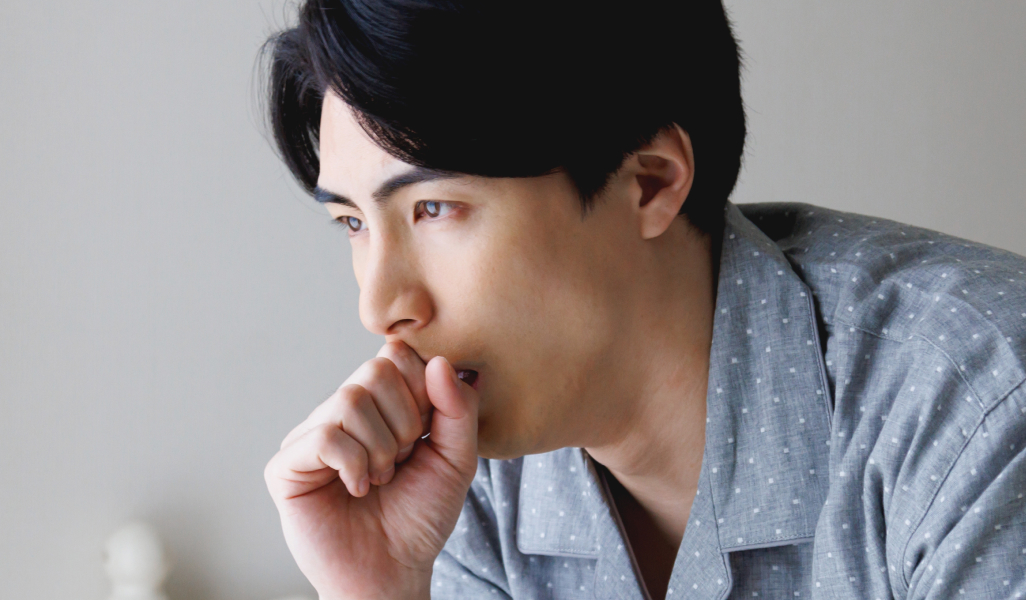『働く人のためのメンタルヘルス対策セミナー』レポート!企業がいまやるべきこととは?

主婦の友社では6月18日(水)、目黒セントラルスクエアにて『働く人のためのメンタルヘルス対策セミナー』を開催しました。 このセミナーは、いま日本企業に強く求められている「健康経営」をこれまで以上に推進したい人事労務、経営企画を担う方々に向けたもの。従業員のメンタルヘルスケアに関する基礎的な知識を得て、現場での具体的な対策を考える一助となればと、雑誌『健康』とウェルビーイングサポートデスクが企画しました。
この日、最初のプログラムは、北里大学医学部公衆衛生学教授、堤 明純(つつみ・あきずみ) 先生によるセミナー。労働とストレスに関する研究の第一人者であり、厚生労働省「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」委員などとしてもご活躍中の堤教授に、『職場のメンタルヘルス対策のヒント』というテーマでお話しいただきました。
従業員全員のリテラシーを高め、それぞれが役割をもってメンタルヘルス対策を行うことが大事

職場におけるメンタルヘルス不調者は右肩上がりに増加しており、仕事や職場に悩みや不安をもつ人は8割にも上ります。内容として最も多いのが「仕事の量」、「仕事の失敗・責任の発生」がほぼ並び、そのほか「仕事の質」「対人関係(セクハラ、パワハラ含む)」「会社の将来性」「顧客や取引先からのクレーム」など。
また全国調査で、メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所は、従業員数300人超の大規模事業所ではほぼ100%なのに対し、50人未満の小規模事業所では6~7割と対策が進んでいないのが現状だといいます。
メンタルヘルス対策の基本は予防。一次予防は従業員や管理監督者への教育を通して、ストレスに気づき、支援する、さらに職場環境の改善につなげるもの。二次予防は不調を早期に発見し、適切な対応を行い、三次予防は不調となった先に、さらに問題が広がらないよう、職場復帰を支援するというものです。
現在、義務化されているストレスチェックテストはそのためのツール。定期的な検査によって、自らのストレスに気づいてもらい、また集団的な分析で職場環境を改善する、それが主たる目的です。ストレスの高い人を早期に把握した場合は、事業所内の衛生管理スタッフや産業医、状況によっては外部の専門家につなげます。
「ふだんから従業員と接している管理監督者はキーパーソンですが、専門家ではないので、病気の診断はできませんし、できる必要もありません。ただし、どんな病気でも、メンタルの不調は仕事の能率、パフォーマンスに表れるので、管理監督者は気づきやすいでしょう。気づいたときにどう動いたらいいか、そのための相談窓口や、組織としての体制をあらかじめつくっておくことがポイントです。
要は、教育や研修によって事業所全員のリテラシーを高め、それぞれが役割をもってメンタルヘルス対策を行っていくことが大切。これは一朝一夕にできることではありません。まず、どんな組織になりたいかという方針があり、それを達成するための中長期的な目標を設定し、段階的に計画を立てて少しずつステップアップします。うまくいっていたら続け、具合が悪ければ改善するという、PDCAを回していく形で、課題を解決していけることが理想です」(堤教授)
ふだんから「話しやすい職場環境づくり」が肝要。部下のメンタル不調は上司一人で抱え込まない

「安心安全な職場づくりが、健康経営のベース」と締めくくられた第1部に続くプログラムは、堤教授と、カルチュア・エンタテインメントグループ上席執行役員の西田宏(にしだ・ひろし)氏によるトークセッション。
西田氏は人事、総務、ITなどを統括するPeople Experienceデザイン本部長も兼務しており、日ごろ現場で感じているヘルスケア対策の疑問に対し、堤教授にお答えいただきました。
第1の質問は「従業員から調子が悪いと申し出があったときに、上司はどのような対応をするのがよいのか、判断の軸などがあれば教えてください」というもの。
「初動を誤ると、かえって事態を悪化させることもあるのかなと思う」という西田氏に対して、堤教授は「まずは話を聞くことです。そのときには、どんな面接でも同じですが、他の人にはわからないように、場所や時間をきちんとセットして、話しやすい状況設定にするということですね」。
話を聞いてみて、これは自分の手には負えないと思ったら、専門家につなぐ、相談や受診などのアドバイスをします。そこまでではないということなら、そのときにすべてを解決しようとせず、時間をおいて、また話す機会を設けても。 「上司としてできることはまず業務量の調整でしょう。できる範囲でフォローしてかまわないですし、部下と話しやすい関係性をふだんからつくっておくことも心がけたいですね」(堤教授)

第2の質問は「明らかに不調なのに、それをかたくなに認めない、大丈夫だと言い張る部下にどうアプローチしたらよいか」。
本人が認めたくない理由の背景をうまく引き出せればいいのですが、難しい場合はやはり上司が自分で抱え込まず、社内の健康管理スタッフや専門家に相談を、と堤教授。
「基本的なスタンスとしては、あなたの健康が心配だ、ということです。法律上従業員を強制的に医療機関に連れていくことはできませんが、家族に伝えて協力して動かすことは可能です。人権やプライバシーの問題には十分気をつけなくてはなりませんが、極端なケースで自殺などが懸念されるときなどは、事業者には安全配慮義務がありますので、対応しなくてはなりません。また、別の話にはなりますが、会社としては、本人にきちんとケアをしてきたという記録を残しておく必要があります」
第3の質問は「メンタルヘルス不調で休職者が出た場合、またその人が復職する場合、上司や同僚はどう対応するとよいか」。
休職する際も、復職する際も、現場でどこまで知らせるかは、本人の同意が大前提ですが、配慮のために必要な情報は共有しておきたいもの。
「周囲は業務のフォローやカバーをしていかなくてはならないので、協力を得るためにも、今後の見通しなどはわかる範囲で伝えていきたいところです。ただ、就業配慮に関わるところ以外では、職場でのコミュニケーション面は、以前通りが原則ですね」(堤教授)
一方、会場の参加者からは、「コロナ禍後、リモートワークを導入しているが、メンタルヘルスにどんな変化があるか教えていただきたい」という質問がありました。
もともとリモートワークは、自由度の高い働き方として導入が推奨されていましたが、準備が整う前にコロナ禍となり、そのため十分な体制がとれず、長時間労働になりやすい、事業者側がパフォーマンスを把握しにくい、管理が難しいなどの課題が出てきました。 「最近言われているのが孤立の問題です。それらの様々なリスクに対しては、やはりリモートでも、できるだけコミュニケーションを維持して、会社との接点を保つようにすることに尽きるんじゃないでしょうか」(堤教授)
実践女子大学と主婦の友社による 産学連携プロジェクトを今年7月に開始
その後、雑誌『健康』が創刊50周年を記念して設けた「すごい!健康長寿アワード」の報告・告知をはさみ、最後のプログラムとして、「実践女子大学と主婦の友社による産学連携プロジェクト」について、社会連携推進室長・深澤晶久教授と文学部4年の吉山香佳さんから説明をしていただきました。

このプロジェクトは、「企業のウェルビーイング(働く人の健康・幸福・働きがい)」がテーマ。個々の企業の職場環境について、Z世代である大学生の視点からアイデアを出すとともに、雑誌『健康』による取材などを通して外部へ発信していく取り組み。7月以降、当サイトにて本プロジェクトに参加いただける企業の募集を開始する予定です。ぜひご覧いただき、ご協力いただければ幸いです。
セミナー終了後の参加者へのアンケートでは、「日々の業務で直面している問題ですが、基礎が大切であることを痛感しました」「従業員が健康的に働くことで、組織全体の生産性の向上が期待できるので、従業員への研修などで理解を深めていければと思いました」といった声をいただきました。
また「ヘルスリテラシーの高め方、正しい情報をどう得ていくかを知りたい」「いろいろな事例紹介を含め、メンタルヘルスについてのセミナーを今後も期待する」などの数々のご意見も。これらの声を参考に、今後もウェルビーイングに関わるテーマに積極的に取り組んで参ります!
まとめ/山岡京子
カテゴリー
サービスメニュー
-
ヘルスケア
コンテンツHealth Care -
メンタル
ヘルスケア
コンテンツMental Health Care -
家事サポート
オフタイム
コンテンツHousework Support Off Time -
目標設定
コンサルティングGoal Setting Consulting -
研修
Training -
カンファレンス
セミナーConference/Seminar -
健康宣言報告書
Health Declaration Report