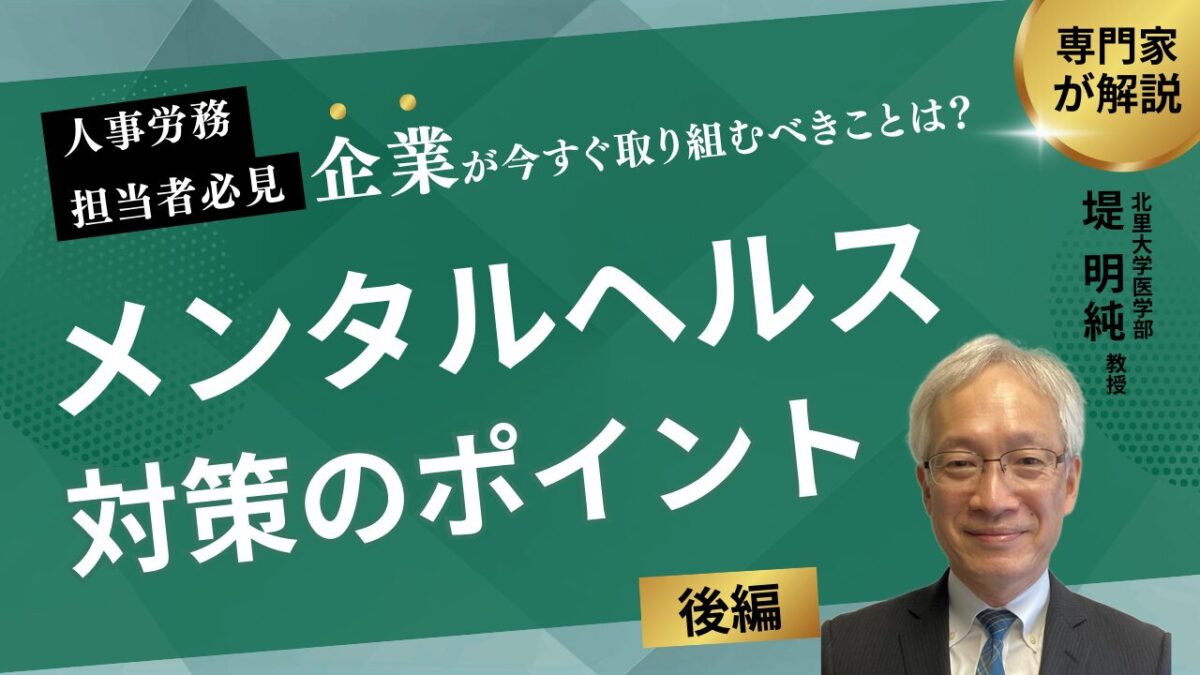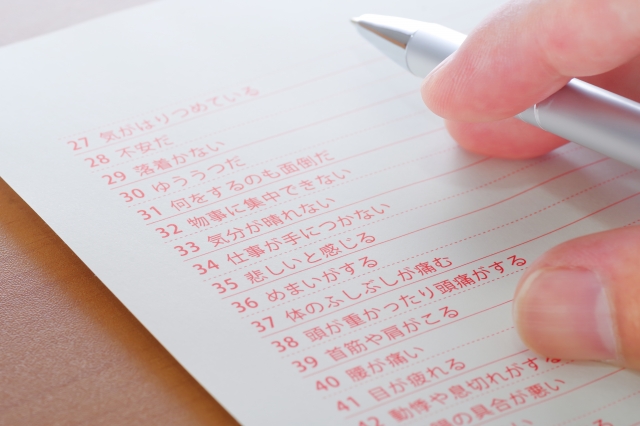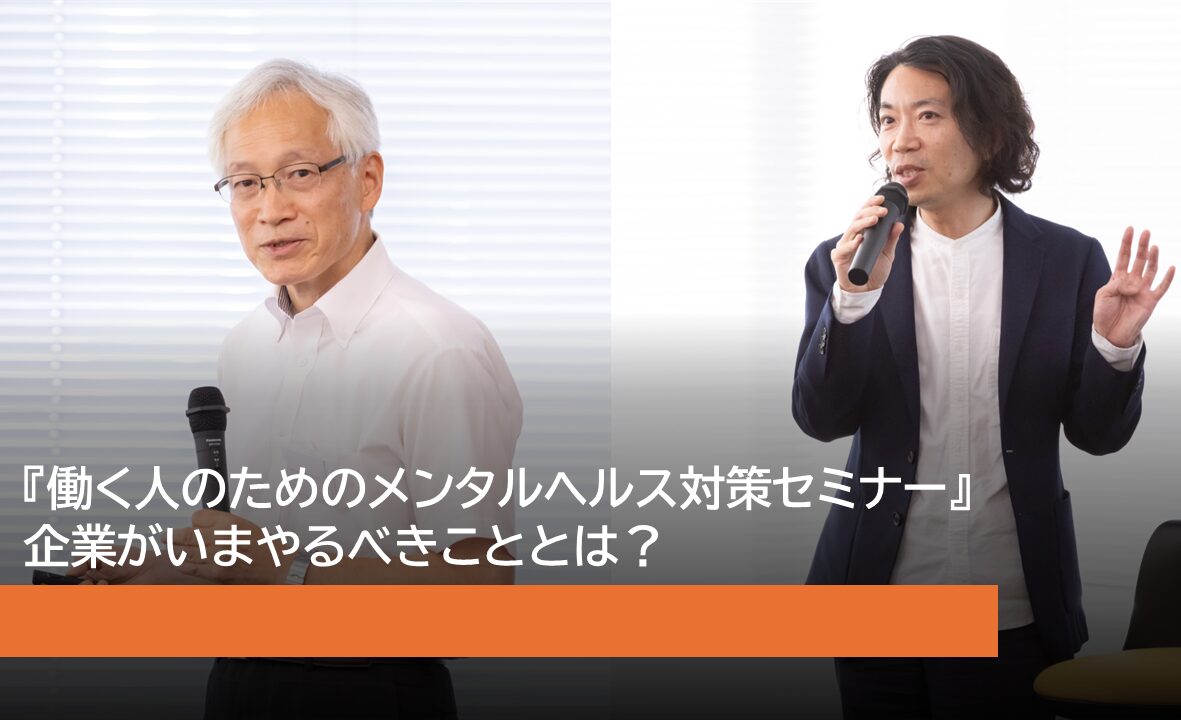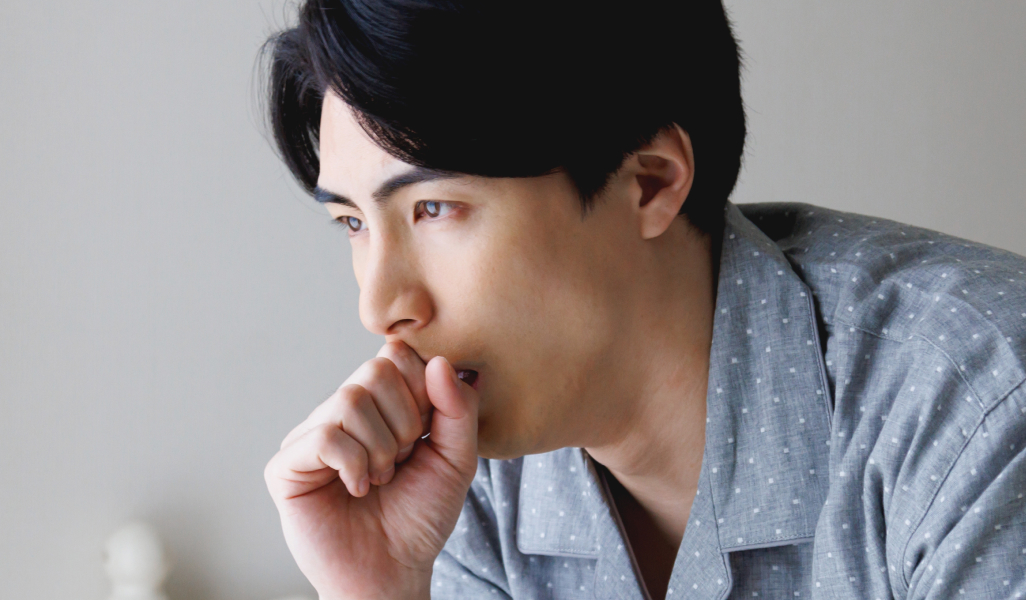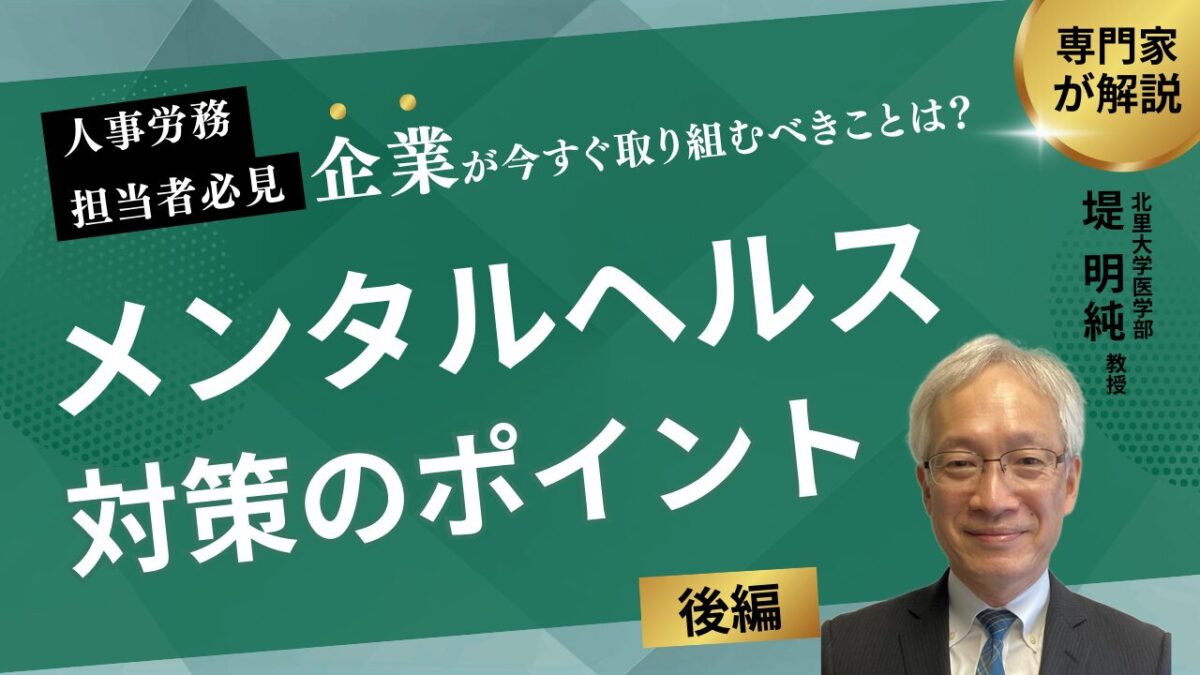
メンタルヘルスの不調により、休業または退職を余儀なくされる労働者が右肩上がりで増加しています。企業として従業員のメンタルヘルス対策をどのように進めたらよいのか、労働とストレスに関する専門家である北里大学・堤明純先生への取材記事【後編】です。
▶前編はこちら
ストレスチェックを有効活用するには職場の環境改善につなげることが重要
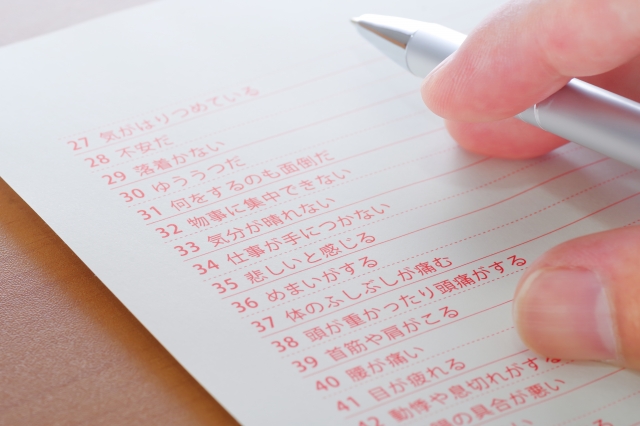
――メンタルヘルス対策の柱はストレスチェックテストだと思いますが、企業にとってこの制度を利用するメリットはなんでしょうか?
堤:50人以上の従業員がいる事業所に、年1回のストレスに関する検査(ストレスチェック)を義務づける制度が始まったのは2015年ですから、ちょうど10年が経つところです。
メンタルヘルス対策には1次予防、2次予防、3次予防があり、不調にならないようにするのが1次予防で、ストレスチェックはそのためのツールです。労働者が自分のストレス状況に気づき、またその結果を企業側は集団で分析することによって職場環境の改善につなげます。検査をする中でメンタルヘルス不調の方が見つかり、そのケアをするのが2次予防、不調になった方の復職支援と再発防止が3次予防ですが、ストレスチェックのメインの目的はやはり1次予防です。
制度開始後にストレスチェックの効果評価を行ったところ、事業者からは「心の健康づくりの計画が進捗した」とか、「メンタルヘルス対策の重要度が増加した」「早期発見と対応の対策を新規に開始した」などの声が増えました。中でも一番多かったのが、「メンタルヘルス対策の方向性が拡充された」という回答でした。
また、労働者と事業者双方にどんなメリットがあったかを伺うと、労働者では「自身のストレスを意識することになった」、事業者では「社員のセルフケアへの関心度が高まった」「メンタルヘルスに理解のある職場風土の醸成」が多く挙がりました。やはり関心を持っていただくことが1次予防の最初の大切な部分です。それを知らずに、メンタルヘルスには怖い病気があって、それにかかったら大変で隠さなくちゃいけない、というような状況では、対策が進みません。
――10年が経過して、ストレスチェック制度の現状についてはいかがでしょうか? メンタルヘルス専門の担当者がいないなど、いろいろな事情で実施が難しい職場もあると思われますが。
堤:ストレスチェックを受検し、かつ職場環境改善を合わせて経験した労働者は、心理的なストレス反応が大きく減り、仕事のパフォーマンスも上がるという調査結果が出ています。フルスペックで対策していただくのが一番効果があるということですね。
その意味で、私自身は対策が伸び悩んでいるんじゃないかというふうに感じています。なぜならストレスチェックは行っていても、それを活用した職場の環境改善はまだまだ進んでいない状況があるからです。そもそも小規模事業所ではストレスチェックは義務化されていません。厚労省は今後対象を拡大していく方針ですが、メンタルヘルス対策にはコストがかかるので、敷居が高いという感覚も確かにあります。
多くの企業では「職業性ストレス簡易調査票」を利用されていると思いますが、その使い方が浸透していないということかもしれません。調査票には、職場のストレスを見える化できるなどのマニュアルもセットされていますが、十分には使いこなされていないのでしょう。
職場にあるストレスは必ずしも目に見えないものばかりではない

――職場の環境改善については、まずどんなことから始めるのがいいと思われますか?
堤:ストレスチェックによって、従業員が自分のストレスに気づき、セルフケアすることがスタートですが、結果を返されて問題を自覚した従業員が、自発的に相談できるインフラが職場にないと、そこで止まってしまいます。 なので、職場でメンタルヘルスに関する相談体制をつくることを、最初にセットで進めるべきです。企業内だけで難しければ、外部の専門家とネットワークを組んだり、自治体や国の相談窓口を紹介することもできます。
職場の環境改善というととてもハードルが高くて、何から手をつけたらいいの、と思われがちですが、シンプルに言えばストレスの要因を外していく、減らしていくことで、より心地のいい職場にしていく、ということです。長時間労働にしても、いかになくしていくかは、それぞれの職場によってやり方は違うはずです。作業効率を上げていくことかもしれないし、事故を減らしていくことかもしれない。例えば、病院では患者さんが来るのを止めることはできないわけで、その場合はスタッフのシフトをうまく組むようにするとか、休みの時間をちゃんととれるようにするなどが考えられます。
あと、ストレス要因はすべてが心の問題ととらえられがちですが、実は暑い、寒いといった物理的な環境や化学物質など、身体的なストレスも含まれます。コロナ禍のときに、医療従事者の方々は時間的な制約や感染予防対策で大変だったわけですが、その他に社会的なストレス、医療現場で働く人とおつきあいしたくないと言われるとか、子どもがいじめられるなどといった問題もありましたよね。
申し上げたいのは、ストレスは必ずしも目に見えないものばかりではなくて、仕事をきつくする要因はほんとうにさまざまだということです。それをいかになくしていくかが職場環境の改善なんですね。ストレスチェックの実施により、そうした要因を見つけて除いていくことが、メンタルヘルス対策のベースだと思います。
メンタルヘルス不調は、仕事面や言動・態度に表れることが多い

――管理監督者の方は現場のマネジメントに忙しくて、なかなか部下のメンタルヘルスにまで目が届きにくいこともあるんじゃないでしょうか?
堤:個人のストレスチェックの結果はご本人のみに通知されます。しかし、従業員のメンタルヘルスに問題がないかどうか、まず気づくのはやはり職場の上司、管理監督者の方でしょう。誰かが不調になれば、職場全体が困るわけですから、どういうふうに部下の相談にのったり、情報提供や助言をしたらいいのか、もし自分では対処できないと不安を感じたときには、なるべく早く専門家につなぐなど、管理監督者に対する教育研修を行うことも大切です。
メンタルヘルスは見えないことばかりではなくて、勤怠に現れることも多いんです。月曜日に休みが多くなるとか、仕事にミスが重なるとか。仕事面は管理監督者がチェックできるポイントで、これまでできていたことができないとき、「なにか心配事でもあるんじゃないの?」という感じで声をかけられます。その他、例えば身だしなみが悪くなる、奇妙な服装をする、表情が乏しくなる、動作が鈍くなるなど、言動や態度に変化が表れることもあります。
ただし、うつ病でも同じですが、表情が暗くて元気がないというときも、「以前と比べて」がポイントです。奇抜なファッションをしていても、口数が少なくてあまり話さなくても、それがその方の個性で、普段通り仕事をこなしているなら問題はないわけです。
メンタルヘルス不調で休職者が出るケースを想定し、手順を決めておくとよい
――実際に職場でメンタルヘルス不調の方が発生した場合の望ましい対応についても教えていただけますか?
堤:心の健康問題によって休職した方の職場復帰支援の手引きを厚生労働省が公開しています(https://www.mhlw.go.jp/content/000561013.pdf61013.pdf)。休業開始から復帰まで、各ステップごとに具体策がありますので、それに沿って進めていただくのが一つの方法です。
何カ月か休職されていた方が戻ってくるときは、以前通り元気というわけではありません。まずご自身に復職の意思があり、主治医の復職可能の診断書がある、その2点がセットで始まるというのがセオリーです。
2点がそろっても、その後すぐに復職していただくのではなく、関係者が集まって状況を確認し、何カ月は残業や出張はなしにするなど、就業制限の配慮に合意したうえでスタートします。その後再発もなく仕事が続けられているようなら、その配慮の部分を少しずつはずしていきます。少しずつパフォーマンスを上げて軟着陸していくわけですが、もちろんなかなかうまくいかない現実もあるかもしれません。
企業としては事例が発生する前に、こうした手引きを参考に、誰がどういう役割を果たしていくのかなど、復帰の手順に関して一応の決めごとをつくっておくことが必要でしょう。その時々で対応が違ってしまうのは好ましくありません。個別の部分はその決めごとに当てはめながら応用していく感じですね。
――メンタルヘルス不調はいつ、どんな形で起こるかわからないので、普段から少しずつインフラを整えておくことが大事ということですね。
堤:働きやすい職場づくりというのが、メンタルヘルスづくりのベースです。何かあれば相談できる、職場では解決できない部分は専門家につなぐシステムや土壌があることが重要で、会社が自分たちの健康について配慮してくれていることは、従業員の安心や安全につながります。 私たちは仕事だけでなく、日々生活をしていますので、いくら職場で気をつけて対応しようとしても、メンタルヘルスの問題は発生するんですね。職場で100%予防するのは無理がありますし、すべての問題に企業が責任を持たなくては、と過大に考えるのではなく、できることから少しずつ進めていただければいいと思っています。
――どうもありがとうございました。
主婦の友社「ウェルビーイングサポートデスク」では、企業の健康経営・メンタルヘルスサポートをお手伝いいたします。こちらからお気軽にお問合せください。
取材・文/山岡京子
●お話を伺った方●
堤明純さん(つつみ・あきずみ)
北里大学医学部 公衆衛生学 教授、日本産業ストレス学会 理事長、厚生労働省「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」委員。自治医科大学医学部卒業。岡山大学大学院 衛生学・予防医学分野 助教授、産業医科大学 産業医実務研修センター 教授を経て、2012 年より北里大学医学部にて教鞭をとる。労働とストレスの健康的な影響とその予防や、労働者の健康の社会格差・メカニズムの解明とコントロールに関する研究などに精力的に取組んでいる。令和3年度「厚生労働大臣 功績賞」、令和4年度「中央労働災害防止協会 顕功賞」、日本産業衛生学会「学会賞」(2023年)ほか受賞歴多数。著書(共著)に『医師による面接指導マニュアル1 高ストレス者編』『基礎から学ぶ健康管理概論』『職場におけるメンタルヘルスのスペシャリストBOOK』など。